今回紹介するのは、ジョン・ダニング著『愛書家の死』です。
あらすじ
著名な馬主が亡くなり、その右腕だった男が古書店主クリフを呼び出す。
依頼は、馬主の20年前に死んだ妻が生涯をかけて集めた蔵書の鑑定と、彼女の死後に何者かに盗まれた蔵書の一部の行方を突き止めることだった。
しかし、盗まれた本は市場に出回った形跡がまったくなく、謎は深まるばかり。
古書界と競馬界を行き来しながら真相を追うクリフは、蔵書に隠された一人の女性の不可解な死へと迫っていく。
古書薀蓄と競馬への愛が詰まった人気シリーズであり、蔵書狂という言葉がここまで皮肉な意味を帯びる物語は他にない。
古書鑑定から始まるストーリー
序盤の導入では、主人公であるクリフが依頼元の蔵書を確認するシーンから始まります。
古書の鑑定という感情を切り離した仕事を、クリフは淡々と進めていきます。
しかし、その蔵書の持ち主である人物はすでにこの世を去っており、さらに不可解な死を遂げたのはその妻、キャンディスでした。
実は、大量の蔵書を蒐集していたのは、亡き妻キャンディスの方です。
彼女は筋金入りの古書コレクターであり、その徹底ぶりは並外れていました。
キャンディスの児童書への愛はつきることがなかった。後年、大人向けの文学や歴史書に興味の枠を広げていったが、保存状態のいいハンス・クリスチャン・アンデルセンや、十九世紀初頭の赤ずきんちゃんの本などは、いつも目の色を変えて探していた。
ウィリスはつづけた。
「はじめからキャンディスは完璧主義者だったよ。十五歳のときにすでに、本の表紙や中身に汚れのある本は買わなかった」
趣味である古書蒐集においては、キャンディスは完璧主義者であったようです。
一冊一冊にこだわり、状態や版に至るまで妥協を許さない姿勢が、蔵書の充実ぶりに表れています。
一方で、彼女が生前かかわった人物たちからは、次のような証言も残されています。
おれたちはみんな彼女のことが大好きだった。特におれはね。理由があるんだ。
一九六六年に息子の葬儀に金を出してくれたんだよ。そのことは、誰にも知られていなかったし、いまだって知る者はいないよ。
心づかい、なんてものじゃなかった。息子のジェイソンは馬に頭を蹴られて死んでしまったんだ。
キャンディスが葬儀代をだしてくれたのさ。
どうやら、キャンディスは大変人望のある女性であったようですが、そんな彼女に恨みを抱いていた人物が本当に存在するのでしょうか。
彼女の蔵書から盗まれた本の行方、そして彼女の不可解な死を考えると、すべてが煙に巻かれたような印象を受けます。
主人公クリフは、まるで彼女がこの世に残した足跡を一つずつ拾い上げるかのように、情報を丁寧に収集していきます。
当初は感情を切り離し、淡々と古書の鑑定を進めようとしていたクリフですが、彼の姿勢は次第に変化していきます。
事件の裏に潜む人間模様やキャンディスが遺した謎に引き込まれ、彼自身がこの物語の深い沼へと足を踏み入れていくのです。
推理モノとしての展開
推理小説という意味で、必要最低限の情報で事件を解決する主人公と、行き当たりばったりで進みながら結果的に事件を解決する主人公。
この2つは、性格的にも物語の展開にも対極にありますが、本作は明らかに後者――行き当たりばったりの主人公が描かれています。
その主人公が生み出す“余白”、つまり悪く言えば寄り道や無駄足といった部分が、かえって作品の主題と絶妙に調和しているのがポイント。
競馬や古書といったテーマとともに、何かを探してもすぐに答えにたどり着けるわけじゃない―そんな偶然の重なりと不確実性に満ちた作品です。
なので主人公が寄り道して無駄に見える行動が、むしろ良い意味で競馬業界の裏側や古書探索のスリルとリンクしていて、結果的に作品の味わいを膨らませています。
物語の序盤で登場するのが、シャロンという女性。
彼女は莫大な資産を背景に、馬を保護する活動をしている重要人物です。
クリフは彼女に聞き込みのため接触しますが、その際にただ話を聞くだけでなく、なんとシャロンの活動を手伝い始めます。
しかも、すぐにその場で彼女の手伝いを了承して、厩舎での日々は肉体労働に明け暮れるという展開に。
ここで、普通の推理小説の主人公なら「そんな無駄なことしないで早く情報を引き出せよ」と思うかもしれませんが、ここがクリフのユニークなところ。
彼は、何事も一度自分で体験してみないと納得しないタイプなのです。
この“回り道”とも言える捜査方法は、クリフが警察から古書店経営という異色の経歴を持つ点にも表れています。
要するに、クリフはとにかく現場で何かを掴むまで動き続ける。机上の空論ではなく、実体験からすべてを導き出すのが彼のやり方なのです。
そんな彼が、続いて厩舎での仕事を体験し始める場面は、競馬の世界が描かれていて一般読者から見ても興味深い部分です。
単に事件を追うだけではなく、競馬の世界観が広がりが単純に面白い。
主人公の行動は、一見無駄のように見える寄り道や余白を生み出しますが、それが結果的に事件解決のカギになり、物語にリアルな不完全さを与えています。
こうした寄り道があるからこそ、最後にすべてがつながるときのカタルシスが大きいのだと感じます。
決して簡単には推論を導き出せない状況だからこそ、クリフの寄り道こそがこのシリーズを面白くしているんです。
アメリカの古書業界について
最後に少し本作でも触れられている、アメリカの古書業界についてまとめてみます。
どうやら、アメリカの古書業界自体は、非常に商業規模が大きいようです。
国内外のバイヤーが集まり、オンラインオークションや古書フェアを通じて何十億ドル規模の取引が行われているそう。
特に文学、歴史、初版本、サイン入りの書籍、稀覯本(きこうぼん)が高い需要を持ちます。
例えば、アメリカーナという部類のアメリカ建国に関する歴史が書かれた揺籃期本(ようらんきぼん)やアメリカ文学の初版本は世界中の収集家にとって垂涎の的。
「アメリカンドリーム」にも通じますが、一冊の古書が巨額の富を生むこともあり、例えば初版本が後にプレミア化し、何十倍にも価格が跳ね上がるケースがあったり。
著者も一時期に稀覯本専門店を経営していたので、この辺りの事情は、噛めば噛むほど出てくるという感じです。
稀覯本と一般的な古本が混ざって市場に流通している日本とは違って、アメリカでは稀覯本専門店やオークションでの取引が明確に区分されています。
とくにアメリカの古書市場には、膨大な情熱と知識を持つ収集家がいて、彼らがただのコレクターにとどまらず、歴史の一部を守る存在であることが物語にも反映されています。
アメリカーナ専門家とは?
アメリカの歴史や文化に関連する古書、文書、地図、印刷物などを収集・研究する人たちのこと。揺籃期本(Incunabula:インキュナブラ)とは?
揺籃期本というのは、一般的に1455年頃から1501年までに印刷された書物のことを指す。
グーテンベルクの活版印刷が誕生した直後の時期に作られた、いわば「印刷物の揺籃期=誕生期」に作られた本。
世界的に貴重で、もちろんアメリカの古書市場でも非常に高い価値がつけられることが多いらしい。
何故アメリカーナ専門家が揺籃期本に注目するのかというと、実はヨーロッパで作られていた揺籃期本にはアメリカの歴史に関わる稀少な文書や地図が含まれているからなのです。
有名な揺籃期本の例
『コロンブス航海記』(1493年)
コロンブスが新大陸を発見した航海の記録をまとめた本。
アメリカについての情報はすべてヨーロッパで印刷されていたため、初期のアメリカ関連資料はほとんどが揺籃期本にあたる。『ニュルンベルク年代記』(1493年)
ドイツの医師であり人文学者のハルトマン・シェーデルが編纂した世界史の書物。
多くの木版画が挿入され、中世からルネサンスへの移行期の世界観を伝えている。当時の主要都市の図版や歴史的出来事が詳細に描かれている。
これらは、印刷技術の黎明期における貴重な文化遺産として、高い歴史的価値を持っており、それぞれの書物が当時の知識や思想の広がりを象徴しています。
現在でも多くの研究者やコレクターにとって重要な存在のようです。
少し脇道にそれましたが、専門的な経験則でしか描けない小説は、読んでいるとどこか新鮮でワクワクするもの。
未知の世界を覗き見ているような感覚があって、自然と好奇心がかき立てられ、気づけばどんどんページが進んでしまいます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
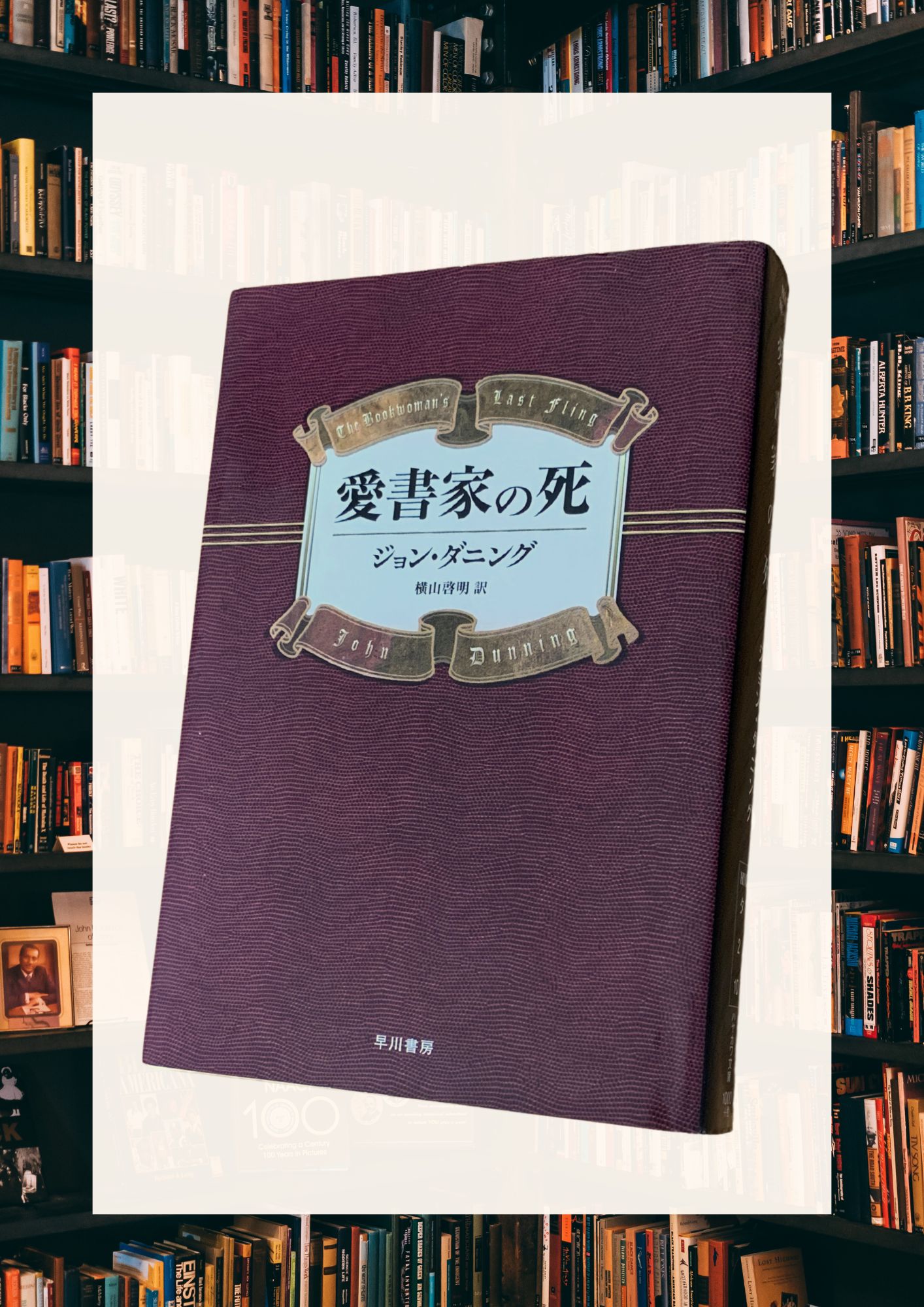
コメントを残す