今回紹介する本は、『波濤風雲録 時代小説の楽しみ12』です。
波濤風雲録(はとうふううんろく)
聞きなれない言葉ですが、波濤(はとう)は「大きな波」「荒れた海」を意味します。風雲は「物事が急激に変化する情勢や、大きな動き」を指します。
この2つをあわせた「波濤風雲録」という言葉には、「荒波や激動の情勢の中で起こる出来事を記録したもの」というニュアンスがあります。
本書は、時代小説の中でも海を越えた外交や貿易を題材とした作品を集めたアンソロジー集です。
その中でも特に印象に残ったのが 『元寇秘話』(新田次郎著) です。
私はこの作品を読む前、元寇を退けた日本について、一般的な教養の範囲で「神風が蒙古軍を追い払ったおかげで勝利した」という認識を持っていました。
しかし、本作には「松浦党(まつらとう) 」という集団が暗躍する様子が描かれており、当時の乏しい史料をもとに、歴史の裏側に迫る物語が展開されています。
あらすじ
文永五年一月、鎮西奉行の少弐景資(しょうに すけよし)のもとに、高麗からの使者である潘阜(はんぷ)が訪れます。彼は蒙古の国書と高麗の信書を携えていました。当時、日本は高麗や宋とは交易を行っていたものの、蒙古国にはまだ一度も使者を送ったことがありませんでした。
蒙古からの国書は、一見すると丁寧な文言で綴られていましたが、その内容はただの親交を求めるものではなく、武力行使を示唆するものでした。
使者である潘阜の話によれば、蒙古国の支配下に入った高麗は長年にわたって苦しめられており、日本も同様に侵略を受ける可能性が高いと考えられました。しかし鎌倉幕府から九州の武士たちに届いたのは、「蒙古の襲来に備えて防備を厳重にせよ」という、頼りない一片の通達のみ。
九州の勢力だけで蒙古軍に立ち向かうのは到底不可能と判断した少弐景資は、海の向こうの情勢に詳しく、海上での戦闘力を持つ松浦党に協力を仰ぎ、急ぎ防衛計画を練ることとなります。
一般的に知られている元寇の背景
1回目の侵攻(文永の役 / 1274年)
背景:当時の中国を支配していた蒙古国(元)を率いる皇帝フビライ・ハンは、日本を従わせようと使者を何度も送りましたが、日本の鎌倉幕府はこれを無視しました。
侵攻の規模:蒙古(元)、高麗(現在の韓国)、中国南部の兵士を合わせた約30,000人規模の軍勢。
船:約900隻。
戦闘の展開:蒙古軍は九州北部の博多湾に上陸し、現地の武士たちと戦闘を繰り広げました。
日本の武士は一騎打ちを得意としていましたが、蒙古軍は集団戦法や火薬兵器(てつはう)を駆使し、日本側に混乱をもたらしました。
しかし、突如吹き荒れた暴風(台風)が蒙古軍の船団を破壊し、多くの兵が溺死したため、元軍は撤退。
2回目の侵攻(弘安の役 / 1281年)
背景:文永の役での敗北後、フビライ・ハンは再び日本征服を目指し、大規模な準備を開始しました。
侵攻の規模:1回目の倍以上となる約140,000人の大軍が日本に向かいました。
船:4,000隻以上。
戦闘の展開:蒙古軍は九州に上陸しようとしましたが、日本の防衛が強化されていたため苦戦しました。
鎌倉幕府は博多湾沿いに石塁(いわや)という防壁を築き、蒙古軍の上陸を阻止しました。
日本の武士たちが蒙古軍に夜襲を仕掛けるなどのゲリラ戦で応戦。
そして、再び台風(後に「神風(かみかぜ)」と呼ばれる嵐)が発生し、蒙古軍の船団を壊滅させました。
蒙古国は2度にわたって日本征服を試みましたが、いずれも失敗しました。
このとき元軍を壊滅させた嵐は、やがて「神の加護」として語り継がれ、「神風(かみかぜ)」という言葉が生まれることは一般的に知られています。
物語のキーとなる『松浦党』について
元寇(1274年の文永の役と1281年の弘安の役)において、松浦党(まつらとう) は日本の防衛で重要な役割を果たした水軍集団です。
彼らは九州北部の松浦地方(現在の長崎県西部)を拠点とし、元寇における迎撃で他の武士団を凌ぐ存在感を示しました。
松浦党は平安時代末期から存在していたとされ、九州北部の豪族たちを中心に、多くの武士と共に水軍勢力として成長しました。
彼らの活動拠点である松浦地方は玄界灘に面しており、古くから海上警備や交易の要所として知られていました。
松浦党(まつらとう)
■主要な拠点
松浦郡、肥前(現在の長崎県や佐賀県の一部)
■主な活動
・海上交通の監視
・敵の上陸阻止
・沿岸警備
・海賊対策
松浦党の構成員は船舶操作に熟練し、特に海上戦においてその高い戦闘能力を発揮しました。蒙古軍の侵攻に際しても、海上での作戦行動や奇襲戦術によって重要な役割を担い、日本の勝利に貢献しました。
しかしながら、松浦党の史料はあまり多く残っておりません。
いくつか理由が考えられます。
1.地域的な問題
松浦党は九州北部、特に肥前国(現在の長崎県や佐賀県)を拠点にしていた武士団であり、その活動範囲は海上戦を中心としていました。
一方、当時の主要な記録や史料は京都や鎌倉といった政治の中心地に集約される傾向があり、地方の勢力に関する記録はあまり残されていないのが現状です。
鎌倉幕府や朝廷の公文書に記録されるのは、重要な政務や中央で活躍した有力武士が中心でした。
松浦党のような地方の海上勢力は、直接の中央政治への関わりが薄かったため、詳細な記録が少ないと言われます。
2.海上武士団という特性
松浦党の活動の多くは海上で行われました。彼らは、海上武士団であったため、陸上戦のような記録が少ないことも原因のひとつかもしれません。
松浦党は海賊対策や海上防衛、そして交易や倭寇活動にも関与したとされますが、こうした海上での活動は「戦場での記録」に残りにくいのです。
3.倭寇との関わりによる評価の低下
倭寇との関わりが後世の評価を難しくしたのではないかという説です。
松浦党は、鎌倉時代には元寇の防衛に尽力しましたが、南北朝時代から室町時代にかけては一部が「倭寇」として活動していたとされます。
倭寇は略奪や密貿易など違法な行為も含まれており、後世の記録では「反社会的勢力」として否定的に扱われることも多いです。
このため、積極的に残すべき史料として評価されず、失われた可能性があります。
現在残されている松浦党に関する主な史料の一つに『八幡愚童訓』があります。
しかし、その情報も限られており、松浦党を中心とした物語を再構築するためには、当時の背景や前後の史実に詳しく精査することが必要です。
このような点で、本作のように松浦党を題材とした物語は非常に貴重なものだと感じます。
暗躍する松浦党
松浦党は海上武士団としての特性から、陸上戦よりも海上戦でその実力を発揮しました。
しかし、彼らは陸上での戦闘でも、正面からの力押しではなく、巧妙な奇襲作戦や策略を駆使して戦況を有利に進めることができました。
加部島には人はいなかった。逃げ出したばかりのような取り乱し方であった。家財はそのままにしている家が多かった。島は東西半里(二キロ)南北一里(四キロ)の小島であった。船酔いをした兵を休ませるには適当なところであった。
~中略~
上陸した兵たちは、人家のなかにあった、酒の瓶を発見した。
「日本人は酒が好きなんだな」
彼らはこれが松浦党の計画とも知らずに水でも飲むように飲んだ。
一回目の蒙古軍襲来では、長期間の船旅と慣れない環境のため、多くの蒙古軍兵士が船酔いに苦しんでいました。
加部島での休息は絶好の機会に思えましたが、これは松浦党が仕掛けた罠でした。
酒を飲み酔い潰れた蒙古軍兵士たちは、その後の松浦党による夜襲に対応できず、多数の死者を出す壊滅的な被害を受けます。
この奇策により、蒙古軍は大打撃を受け、最終的に一回目の元寇を退ける大きな要因となったのです。
松浦党の指導者であり、元寇の際に大きな役割を果たした松浦氏の一人として知られるのが、松浦定(まつら さだむ) です。
物語にも松浦党の中心的な指導者として登場しますが、実際の歴史的記録においては、松浦党内部に複数の有力者が存在していたため、「松浦定」という名前が特定の個人を指しているのか、指導者全体を総称しているのかは明確ではありません。
松浦定は南宋を訪れた経験が豊富であり、杭州を中心に日本から木材や硫黄などを輸出し、宋銭と交換していました。
この貿易活動によって、南宋の商人たちとのつながりが深く、現地には多くの知人がいたと考えられます。
もともと南宋と日本は友好関係にあったため、南宋が蒙古(元)の支配下に入った後も、その関係は完全には断たれず、密接な情報交換が可能でした。
「たいへんなことになりそうですな。その前にひと儲けというわけですか」
杭州の交易商人の陳陽徳は松浦定の顔を見ると笑いながら言った。
「いや、今度は金儲けに来たのではない」~中略~
「私はなんとかして南宋の艦隊が日本にこないようにしたいのです」
「それは南宋の者に取っても同じ気持ちです。十万という大軍が、日本へ無事行けるかどうかも、分からないし、たとえ、行き着いたとしても、何の恨みもない日本軍と戦わねばなりません。しかも勝つ可能性は少ないのです。」
松浦党は単に武力で戦うだけでなく、南宋に潜入して現地の商人と接触し、情報を収集していました。
彼らは蒙古の支配下に置かれた南宋の内部情報を巧みに探り、南宋側からの内部崩壊を目指したと考えられます。
こうした柔軟な外交や情報戦も、松浦党が元寇で重要な役割を果たした理由の一つです。
まとめ
この時代の戦闘では、明らかに海上戦で攻める側が不利だったと感じました。
元寇の際には、元軍は海を越えて日本に攻め込む必要があり、船旅での食料不足や台風などの自然災害、現地の地理に不慣れなことが大きなハンデになりました。
一方、日本側は自国の沿岸で戦えるため、奇襲や夜襲といった柔軟な戦術で有利に戦うことができました。
さらに、中央政権と地方の温度差も中央の鎌倉幕府は、九州の防衛を現地の武士団に任せきりといった点で描かれていました。
元寇後の中央は神風伝説を強く信じていたため、現実的な外敵の脅威をあまり深刻に受け止めていなかった可能性があります。
しかし、貿易が盛んで異国との接触が多かった九州地方では、外海からの脅威を日常的に感じていたため、防衛に対する意識が高かったのです。
元寇後、九州の武士たちは多くの犠牲を払って戦ったにもかかわらず、十分な恩賞が与えられなかったことが、のちの地方勢力の不満として蓄積し、北条家の崩壊に影響したのかもしれません。
あまり知られていない歴史の裏側を感じることができた作品でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
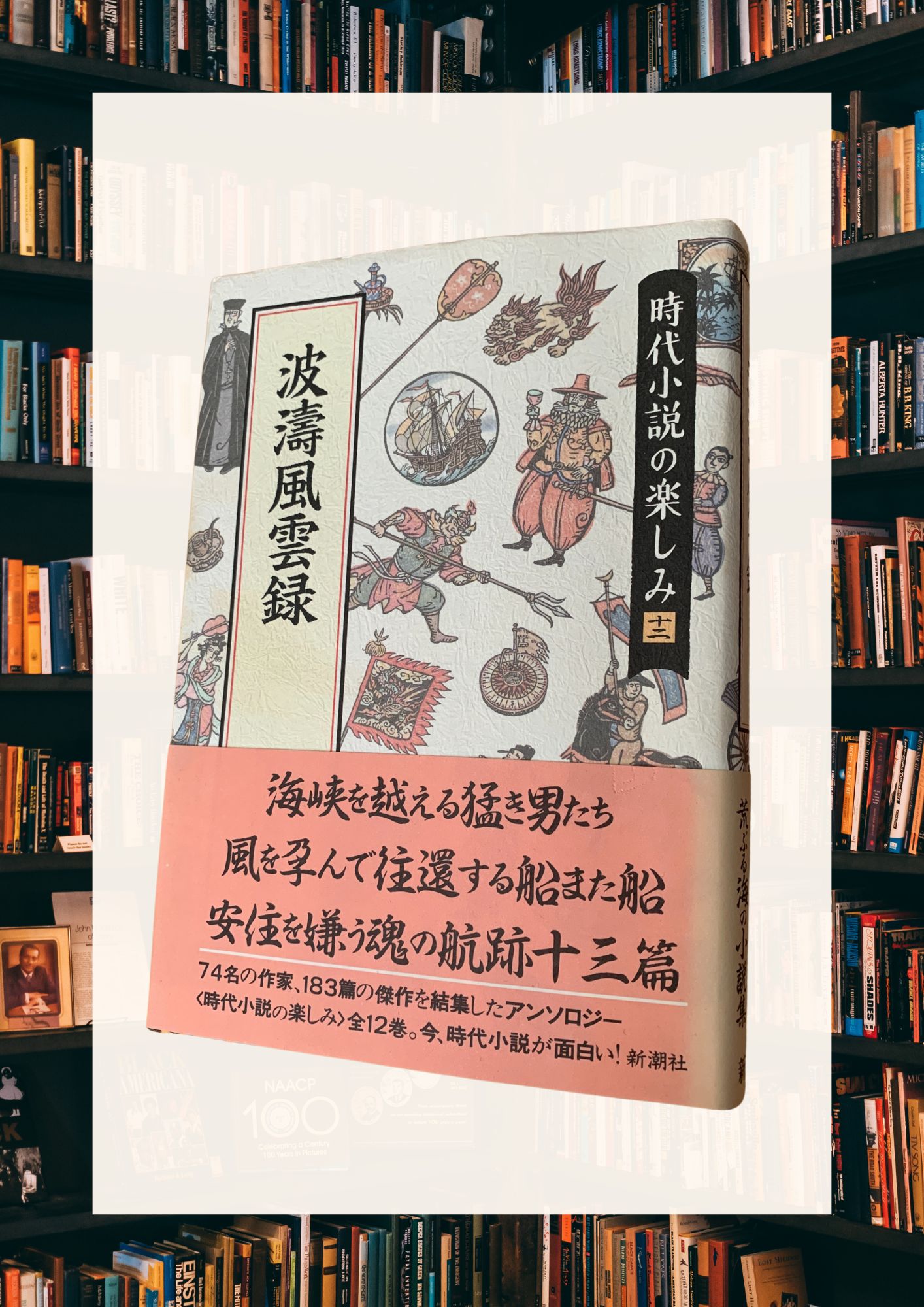
コメントを残す