今回紹介するのは、ジョルジュ・シムノンの『サン・フィアクル殺人事件』。
あらすじ
フランスの田舎町サン=フィアクルに、匿名の手紙が送られる。
そこには「ミサの最中に犯罪が起きる」との警告が記されていた。
その町は、メグレ警部が少年時代を過ごした故郷だった。手紙の内容を受け、メグレはかつての記憶が残るサン=フィアクルの教会に向かう。
ミサの最中、侯爵夫人が席で息絶える事件が起こります。
表向きには心臓発作による死とされますが、メグレ警部は何か裏があると感じ捜査を開始。
故郷での捜査を進める中で、かつての栄光を誇った侯爵家の衰退や故郷の記憶と向き合う形でストーリが展開していきます。
シムノンの数多いメグレ警部シリーズの中でも、彼の出生地に関わる作品です。
地味に見えて鮮烈――メグレ警部の観察眼
フランスの田舎町というシンプルな環境設定で、都会や豪華な屋敷を舞台にした派手なミステリ作品に比べてるとやや落ち着いた印象、さらに登場人物の人数も多いわけではないので、淡々とストーリーが進んでいくように感じます。
彼のかたわらには、司祭が絨毯を見つめながら、少しでも動いたらその姿勢を保つことができないかのように、じっとからだを堅くしていた。
ふたりはそこで、話し合いも、動きもしないで何をしていたのか?
ある場面で、登場人物である2名を見たときのメグレ警部の反応です。
こうした描写は、メグレ警部の「観察眼」を強く印象付けるもの。
本作では彼の観察力や聞き込みといった地に足のついた捜査スタイルが健在であり、物語の軸となっています。
しかし、彼の出生地にまつわる事件という特殊な背景のためか、彼が積極的に推理を展開する場面は多くありません。
そのため、全体的に「派手さ」には欠けると感じられるかもしれません。
読者は、メグレ警部の視点を通じて、自然と物語をフラットに追体験する感覚を味わいます。
派手なアクションや大きな事件の展開ではなく、物語全体に漂う静けさが、自然と登場人物の微妙な心理の動きに目を向けさせます。
こうした「地味さ」は、むしろ作品の独特な魅力であり、派手なミステリとは異なる、じっくりと読み込む楽しさを提供しています。
『ウォルター・スコットの星のもとに』の章
登場人物たちが館の食堂に集まるシーン。
三者三様、それぞれがテーブルのお酒やご馳走を気ままにつまむ晩餐の中で、自然と会話の流れは事件の真相へと向かっていきます。
食堂は、床から天井までの壁一面に張られている彫刻の板張りのおかげで、館の部屋のうちではその特徴を最も失っていない部屋だった。
~中略~
「まるでウォルター・スコットの小説のなかにいるような気がしませんか?」
伯爵が冷静な声で話した。
本章に、「ウォルター・スコットの星のもとに」という名前を付けたのは、シムノン自身が純文学作家としての自負を持っていたことが背景にあるのではないかと思っています。
とはいえ、シムノンはベルギー出身であり、小説を執筆する際にはフランス語を用いていました。
それでも数多く存在するフランス語圏の有名作家ではなく、なぜスコットランド出身のウォルター・スコットを引用したのでしょうか?
(考えすぎかもしれませんが、ちょっと気になりますね笑)
ウォルター・スコットという作家
初代準男爵サー・ウォルター・スコット(Sir Walter Scott, 1st Baronet FRSE, 1771年8月15日 – 1832年9月21日)は、スコットランドの詩人、小説家。ロマン主義作家として歴史小説で名声を博し、イギリスの作家としては、存命中に国外でも成功を収めた、初めての人気作家といえる。
自分なりに3つ理由を考えてみました。
1.登場人物とスコットの「伯爵」という地位の一致
スコットの小説に登場する人物像が、サン=フィアクルの館やその登場人物たちと重なる。
特に館の支配者であった侯爵は、まさにスコットの世界に登場するような存在です。
2.サン=フィアクルの館がスコットの舞台を彷彿とさせる
本章で、食堂の彫刻や豪華な装飾など、館の描写にはスコットの作品に見られる中世的な雰囲気が漂っています。
こうした舞台設定なので、直感的にスコットの小説を連想させたのかもしれません。
3.過去の栄光と現在の衰退というテーマ
スコットの作品では、歴史や文化の変化によって崩壊する貴族社会や伝統が描かれることが多いです。
同様に、『サン=フィアクル殺人事件』でも、侯爵家の没落がテーマ。
こうした類似性がスコットの名前を引き出したのかなと考えます。
シムノンは非常に多作な作家であり、すべてに深い意味を込めたとは限らないかもしれません。
それでも直感的に「ウォルター・スコット」という比喩が飛び出してくるあたり、文学的な感覚やセンスの鋭さを感じざるを得ません。
この章に特別な思い入れを持って描いているように思えます。
事件の重要なアイテム「祈祷書」について
作品中には、子どもが祈祷書を欲しがるシーンがあります。
メグレの視線は少年の視線と出会った。ほんの二、三秒のあいだのことだったが、それだけでふたりはお互いが友だちであることを理解し合った。
おそらく、昔メグレも、ミサ祈祷書の通常文ばかりでなく、ラテン語とフランス語で二列に印刷された典礼の全文のはいった、金縁の祈祷書がほしかった――そしてついに手に入れることができなかった――だからであろう。
私には、こどもが祈祷書を欲しがるシーンがいまいち理解できませんでした。
フランスのミサに参加するカトリックであれば通常はこういった感情が湧きたつものなのか。
今現在は少し違うかもしれませんが、調べると当時のフランスではカトリックが生活の中心。
特に田舎町では、家庭や学校で子どもたちに宗教教育が施され、祈祷書や聖書が身近な存在ということだったようです。
ミサに通うような家庭で育った子どもにとっては、祈祷書が手元にあると「大人の信仰者」のように見えることでしょう。
我々日本人の現代感覚では少し不思議な行動のようですが、当時の状況を考慮するとごく自然な行動ということになります。
祈祷書をめぐって、メグレが少年と視線を交わしお互いを「友だち」と理解し合った瞬間は、信仰の対象ではなく、「祈祷書を手に入れられなかった」という共感の象徴。
作者のシムノンは、カトリックだったにもかかわらず、信仰は保っていなかったという情報もあります。
シムノンが祈祷書を登場させたのは、彼自身が宗教と距離を置いた立場からの憧れを描きたかったのかもしれません。
まだ未読のシムノン作品が沢山残っていますので、少しずつ読み進めていきたいと思います。どの作品にも新たな発見や魅力があるのではないかと楽しみです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
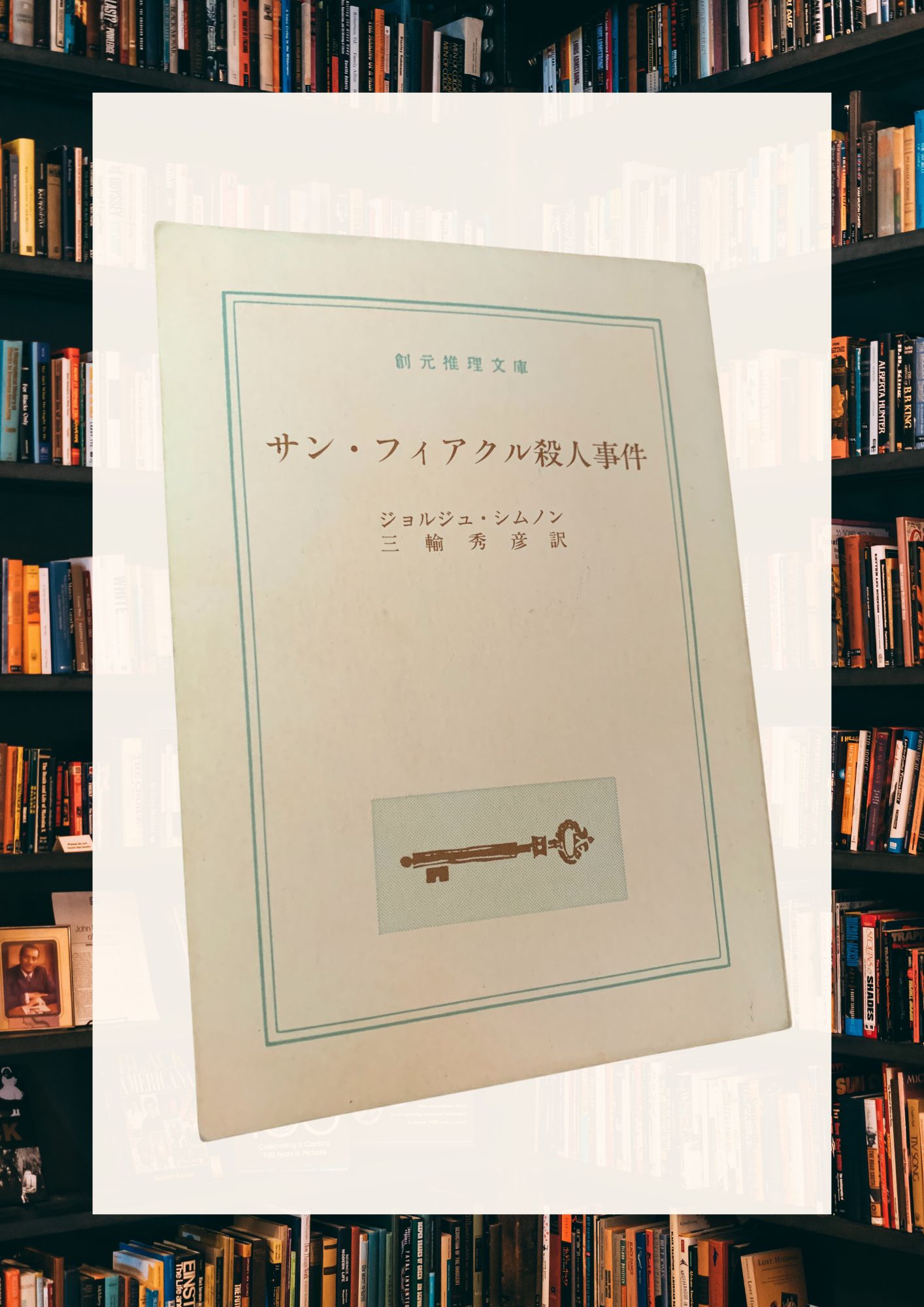
コメントを残す